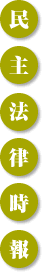 |
 |
 |
- ���Ă̊T�v
�@�c�Ƒ���A�ƋK���̕ύX�ɂ���āu�t���ւ��v��s�ׂɂ��āA���܂蔻�Ⴊ�Ȃ��Ƃ���ł�����̂ŁA���ڂ��ׂ������Ƃ��ĕ���B
�@�����Q�O�N�̗X�����c���̍ہA�X�����Ђ̐ꑮ�����̗A����ЂR�Q�Ђ̂������̂P�S�Ђ��I�ʂ���A����炪�ő��ł��������{�X�֒����i�����j�ɋz�����������`�Łu���{�X�֗A���v�Ƃ����X�֎��Ɖ�Ђ̎q��ЂɈ�{�����ꂽ�B���̍ہA�S�`�p��_�x���̑g�������邱�Ƃ�^�̗��R�Ƃ��Ďq��Љ�����O����A���U�����ߋE�����X�֗A���A���G�A���[���̏]�ƈ��i�S�`�p��_�x���g�����j�P�R���́A���݁A�����̐e��Ђł���X�֎��Ɖ�Ђ��̑��ɑ��āA�@�l�i�۔F�̖@�������ɂ��čٔ��A�J���ψ�����Ă���B���̎����ɂ��ẮA���n�فA���{�J���ψ���ɂ����đg���������̐������˂���ꂽ���߁A��㍂�فA���J�ςɕs���\���Ă����āA�����Ԃ���}���Ă���i��㍂�قł͖{�N�V���Q�X���ɔ������n���������w�肳��Ă���j�B
�@����A�{���̌����ƂȂ��Ă���̂́A�S�`�p��_�x���̑g����������r�I���Ȃ��������Ƃ���A��L�Q�ЂƂ͈قȂ�A�q��Љ����ꂽ�P�S�Ђ̂P�ЂƂ��Ďc���������X�֗A���̑g�����ł���B�����X�֗A�����z�����ꂽ�������ł́A�J��@��c�Ƒ�̊�����Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ������̎蓖�i���̂��Ȃ���Β�z�Ŏx�������j�A�^�s�蓖�i���z��z�Ŏx�������j���������̑g���Ƃ̘J�g����ɂ���Ă��̊�b�Ƃ���Ă��Ȃ������i�J��@�ᔽ�̘J�g����ł���j�B�����Q�P�N�P���A�����X�֗A���͋������ɋz������A�������̋��^�K�����{�ɂ��A���X�֗A���̏]�ƈ��ɕs���v�ɂȂ�Ȃ��悤�o�ߋK����������V�A�ƋK�������肳�ꂽ�i�A�ƋK���ύX�P�j�B���̍ہA�������ɂ�����O�q�̖����̎蓖����������Ɋ܂߂Ȃ��J�g�����^�p�ɂ��ẮA�����X�֗A���̑S�`�p��_�x���g�����ɑ��ĉ���̐������Ȃ���Ȃ������B�Ȃ����̌�A�����Q�P�N�Q���ɋ����������{�X�֗A���ɋz������Ă���B
�@�����X�֗A�����̑��̉�Ђ��������ɍ�������A�ƋK���ύX�P���Ȃ��ꂽ�����Q�P�N�P���ȍ~�A�����X�֗A���̑S�`�p��_�x���g�����ɑ��A�����O�̋����X�֗A������ɂ͐����Ɏx�����Ă����c�Ƒオ�A�������̉^�p�i�����̎蓖�̔����͊��������Ƃ���j�ɂ��x�����Ȃ����ƂƂȂ����B��_�x���g���������̋������Ȃ������{�X�֗A���̎c�Ƒ�̌v�Z���@�͘J��@�R�V���Ɉᔽ���Ĉ�@�ł���ƘJ��ɐ����\���������Ƃ���A�J��͓��{�X�֗A���̈�������@�Ƃ��Đ����w�������A���{�X�֗A�������̎w���ɏ]���Ĉ��̎����ɂ��Đ����Ɏx������ׂ��c�Ƒ�Ƃ̍��z���x�������B���������̊Ԃ̕����Q�P�N�S���A���{�X�֗A���͂��낤���Ƃ��u�����̎蓖�A�^�s�蓖�̔��z�͎c�Ƒ㊄�������̎x�����Ƃ���v�Ƃ����V���ȏA�ƋK���ύX���s�����i�A�ƋK���ύX�Q�j�B�܂�A��@�Ȏc�Ƒ�s�������`���㍇�@�����邽�߂̌Ƒ��������炳�܂ȁu�t���ւ��v���s�����̂ł���B
�@�����Q�P�N�P�P���A�����X�֗A���̑S�`�p��_�x���g�����Q���������ƂȂ�A�u�t���ւ��v�������A�ƋK�����J��@�R�V���Ɉᔽ���A�܂����̏A�ƋK���ύX�͕s���v�ύX�ɂ����薳���ł���Ƃ��āA�������c�Ƒ�ƕt�����𐿋�����i�ׂ���n�ٍ�x���ɒ�i�����B
- ���_�ƍٔ����̔��f
�@�@�����̎蓖���̔��z�����������Ƃ���A�ƋK���͘J��@�R�V���Ɉᔽ���邩
�@������͂������������̎蓖�i�����̂ł���Β�z�Ŏx������j��^�s�蓖�i��z�Ŏx������j�Ƃ����蓖�̐�������A�E���蓖��c�Ǝ蓖�ȂNJ������������m�肳��₷���蓖�Ƃ͈Ⴂ�A���̔��z�����������ł��邱�Ƃ�F�߂�ƁA�Ƒ��蓖��ʋΎ蓖���ȊO�͑S�Ċ��������̊�����ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���J��@�R�V���̎�|��v�p����Ǝ咣�����B�������ٔ����́A�����̎蓖���ɂ��Ă��A���̔��z�����������Ƃ������Ƃł���A���������Ƃ����łȂ����������m�ɋ�ʂł��A���̂悤�Ȉ������J��@�R�V���ɂ͈ᔽ���Ȃ��Ƃ����A�ɂ߂Č`���I�Ȕ��f���s�����B�������A�����炪�����Ƃ��������Ă����A��@�Ȏc�Ƒ�s�������u�t���ւ��v�ɂ���ĒE�@�I�Ɍ`���㍇�@�������Ƃ����A�Ƒ��������炳�܂Ȏ�i���Ƃ�����@���ɂ��ẮA����̔��f�������Ȃ������B�{�����ł͂��̓_���ł����ł���B
�A�@�����X�֗A�����������ɋz���������ꂽ�ۂɁA�������ɂ�����J�������i�����̎蓖���̔��z�����������Ƃ��鈵���j�������X�֗A���̏]�ƈ��̘J�������ƂȂ邩
�@���̓_�ɂ��Ă͋����X�ւ̘J���������������������p���̂������ł���A�������̉^�p�ɂ��Ă͋����X�ւ̏]�ƈ��ɂ͉���������Ă��Ȃ��̂�����A�����炪�z�������̍ۂ̘J�������̕ύX�ɍ��ӂ������Ƃ��Ȃ��A�Ɣ��f�����B
�B�@�A�ƋK���ύX�P�ƏA�ƋK���ύX�Q����̂̂��̂Ƃ��ė��v�ύX�ƂȂ�̂��A�ʈق̂��̂Ƃ��ďA�ƋK���ύX�Q���s���v�ύX�ƂȂ�̂�
�@���̓_�́A���{�X�֗X���Ƃ��ẮA�A�ƋK���ύX�P�ƂQ�͈�̂ł���A��������̂ƌ���Ό�����ɂƂ��Ă͎����L���ȕύX�ł���A������͏A�ƋK���ύX�P�ɂ�闘�v�������ďA�ƋK���ύX�Q�ɂ��s���v���ÎȂ��Ƃ������Ƃł���s�����ł���A�Ȃ��~�X�咣���Ă����B�����������́A�A�ƋK���ύX�P�̒i�K�ŏA�ƋK���ύX�Q��\�肵�Ă����ƔF�肳�����̂́A�A�ƋK���ύX�P�̍ۂɁA�Q�̕ύX�ɂ��ċ����X�֗A���̏]�ƈ��ɑ��ĉ���̐��������Ă��Ȃ������Ƃ��āA�A�ƋK���ύX�P�ƂQ����̂̂��̂Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ɣ��f�����B���_�Ƃ��Ă͐����Ȕ��f�ł��邪�A���������̂悤�Șg�g�݂��Ƃ��Ĕ��f�����ƁA�����A�ƋK���ύX�P�̒i�K�ŏA�ƋK���ύX�Q�̓��e�ł���u�t���ւ��v�ɂ��Đ��������Ă����ꍇ�ɂ́A���̂悤�ȁu�t���ւ��v���L���ƂȂ�]�n�����邱�ƂɂȂ�A�ɂ߂ĕs���ł���B
�C�@�A�ƋK���ύX�Q�ɍ������͂��邩
�@���{�X�֗A����������̍��������咣���Ă��Ȃ��Ƃ��āA�`���I�ɍ������Ȃ��Ɣ��f�����B
�D�@�t���������̐���
�@�A�ƋK���ύX�P�̍ۂɂ͋����X�֗A���̏]�ƈ��ɕs���v�ɂȂ�Ȃ��悤�o�ߑ[�u���Ƃ������ƁA�A�ƋK���ύX�P�̍ۂɏA�ƋK���ύX�Q���ꋓ�ɂ��Ȃ��������{�X�֗A���́u�藎���v����A�ƋK���ύX�Q�������Ɣ��f���ꂽ���ƁA���{�X�֗A�����J��̐����w���ɏ]���Ĉ�薢�����c�Ƒ��������Ɏx�����Ă��邱�ƂȂǂ���A���{�X�֗A���ɏ��@���_���Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��Ƃ��āA�t����������F�߂Ȃ������B
- �����̕]���Ȃ�
�@���ɂ͏������B���������O�ɍs��ꂽ�J���@������i��x���̌X�����e�[�}�j�ɂ����Ă͍�x���̕������f�ɂ��ċc�_����Ă������A�{���͂������ɏ����낤�ƕ������Ƃ���ł��������B�������W���J���Ă݂�A�����ŏ��ɂ͏��������̂́A�������e�͏A�ƋK���ύX�Q�ɂ��č������̎咣���Ȃ��Ƃ������R�ŁA���X�̏����ƂȂ����B���{�X�֗A���̌Ƒ��������炳�܂ȁu�t���ւ��v�̈�@�ɂ��ẮA�ٔ����͉��画�f�����A�܂������̎蓖���̊��������̐��i�������悤���Ȃ��蓖�ɂ��Ă��̔��z�����������Ƃ���A�ƋK�����L���ł���Ƃ���A�Ƃ�ł��Ȃ����e�ł������B��͂��x���͗v���ӂł���Ƃ������Ƃ��v���m�炳�ꂽ�B
�@�����Ƃ��A�{���ł͑����̓��{�X�֗A���̏]�ƈ��ɉe�����g�y����\��������A���̈Ӗ��ł͉���I�ƌ�����ٔ��ł��邱�Ƃ��m���ł���B�����Ă����Γ��R�̂��ƂƂ��Ă��̂܂܈����Ă������ɂ��āA�S�`�p��_�x���̑g�����������Ȃ���������グ�A�ٔ��܂ō\�������ƂŖ�艻���邱�Ƃ��ł����B���̉^���̐��ʂɂ��ẮA�\���ɈӋ`���m�F���ׂ��ł���B
�@�{���ɂ��Ă͓��{�X�֗A���͓��R�̂悤�ɍT�i���������߁A�����������p���ꂽ�t���������ɂ��ĕ��эT�i�����A��㍂�قɂ����Ĕ������e�ɂ��Ă̏�L�̖��_�ɂ��Ă�����������悤�A�S�͂�s��������
- �@�i�ٌ�c�͍�c�@�F�A���c���A�J�^��j
- �͂��߂�
�@���n�ّ�P�������i���c�T�q�ٔ����j�́A�����Q�R�N�T���P�O���A����J�̊X�銈�����֎~���鉼����������s�����B�{���X�銈���́A��Ђ���g�����ɑ����@�s���ȍU�������������A�g������Ў��ӂŒZ���Ԃ̊X����s�����Ƃ������̂ł���B����ɂ�������炸�A�g���̊X�銈�����֎~����Ƃ����{������������́A�܂��ɑO�㖢���̌���ƌ��킴��Ȃ��B
- ���Ă̊T�v
�@�{���̊X��֎~��������\�����Ă��k�`�ό��o�X������Ђɂ́A����J�̑g�����S�����ݐЂ��Ă���Ƃ���A��Ђ͑g�����������A�g�����S���ɑ��āA�ق��~�߁A�z�ԍ��ʁA�s���z�]�A�o�Β�~�����A�ސE�����A�c�Ƒ㖢�����A���R�ސE�����ȂǁA�������@�s���ȍU�����s�����B���̂��߁A���݂S���̑i�ׂ����n�ّ�T�������ɌW�����Ă���A�V���ɂP���̑i�ג�N�ƁA�J���ψ���ւ̋~�ϐ\�������ׂ��������ł������B
�@�����������A�g���́A�R���Q�Q������S���ԁA�e���P�T���قlj�Ў��ӂ��X��Ԃł܂��A�u�k�`�ό��o�X�́A�J���g����G�����A���ق�������ʁA�o�Β�~�����A����ɂ͔z�u�]���ȂǕs���ȍU�����s���Ă��܂��E�E�E����J�k�`�ό��o�X����́A��Ђ̕s�@�E�s���ȑg���Ԃ����������A�����҂̐����⌠������邽�߁A�ٔ��������܂߁A�S�苭���킢�������߂Ă��܂��B�݂Ȃ���̂������������x������낵�����肢���܂��B�v�Ƃ̃e�[�v�𗬂����B
�@����ɑ��āA��Ђ́A�X�銈���y�уr���z��̋֎~�������߂āA��������\�����Ă��̂ł���B���������A�{���̂悤�ȊX�銈���ɑ��āA��������\�����Ă邱�Ǝ��̂��ُ�ł���B
- �܂����̉���������
�@�Ƃ��낪�A�ٔ����́A��Б��̎咣���قڑS�ʓI�ɔF�߁A��Ў��ӂT�O�O���[�g���͈̔͂ɂ����āA�u�X����`�ԓ��̎ԗ��Ŝp�j���A�X����`�ԓ��𗘗p���ĉ������s���A���邢�͕����𗬂��ȂǁA���҂̋Ɩ���W�Q������A���҂̖��_�A�M�p�����������̍s�ׁv�y�сu���҂̖��_�y�ѐM�p������������e���L�ڂ����r����z�z����s�ׁv���֎~����Ƃ̉�����������s�����i�Ȃ��A�g���́A��Ў��ӂ��X��Ԃł܂�������̂́A�r���͔z�z���Ă��Ȃ��B�X�銈�����s���ɂ������Ď������Ɉ��A�ɏo�����A�g���j���[�X��n���������ł���B�j�B�������A���̉���������ɂ́A��̗��R��������Ă��炸�A�{���X�銈�����Ȃ������ȑg�������łȂ��̂��A�Ȃ���Ђ̌�����N�Q�������ƂɂȂ�̂��ȂǁA�ٔ����̎v�l��H���܂�����������Ȃ��̂ł���B
�@��X�́A����̑O���ɁA�g�������̏d�v���Ȃǂ��ڍׂɋL�����咣���ʂ�A�g�����̒q���Ȃǂ̏����o�������A���̂悤�ȉ��̗��R��������邱�ƂȂ��s���Ȍ�����o���ꂽ�̂ł́A�ٔ����͂�����̒�o���ʂ�ǂ�ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ̋^�O���������Ȃ��B
�@�܂��A���̉���������́A�J�����̍ٔ����ł͂Ȃ��A��P�������i�ۑS���j�̍ٔ����ɂ�锻�f�ł���B�J�����̍ٔ������A�K�������J���҂̌����i��ɒ����Ă���Ƃ��v���Ȃ����A���̂悤�ȕs���ȉ�����������s��ꂽ�̂ł́A�g�������̈Ӌ`�ɂ��Ă̗������������ۑS���̍ٔ����ɁA�g�������̓K�@���f�����邱�Ǝ��̂���莋������Ȃ��B
- ����̉ۑ�ƓW�]
�@�ߔN�A�g���̊X�銈���ɑ��āA�ٔ����͑g�������ɑ��闝�������������f�������Ă���A�����l��ł̊X�銈����A�����m���̊X�銈���ɑ��ẮA��������F�߂�s�������A���Q����������F�߂�s�������������A�g���������傫����������Ă���B�������A�{���X�銈���́A�g�����̌����W���ٔ����ŌW�����ɁA��Ў��ӂŒZ���Ԃ̊X������������ł���A�ߔN�̌�����ȂĂ��Ă��A�{������������͖��炩�ȕs������ł���O�㖢���ƌ��킴��Ȃ��B
�@���̂悤�ȕs�����肪�܂���ʂ�̂ł���A�J���g���́A���@�ŕۏႳ�ꂽ�g����������s�����Ƃ��ł��Ȃ����ƂɂȂ肩�˂��A�܂��ɘJ���ҁA�J���g���̍�����h�邪���d��Ȗ��ł���B
�@�g���́A�T���Q�O���t�ʼn������ɑ��Ĉًc��\�����Ă��B����́A�ٌ�c�A�g������̂ƂȂ��āA�{������������̕s�����𖾂炩�ɂ��ׂ��A����Ȃ闝�_����������ƂƂ��ɁA�R�c��`�������̉^����i�߂Ă��������ł���B�ǂ����F�l���ɂ�����܂��Ă��A���x���A�����͂�����܂��悤�X�������肢���܂��B
�i�ٌ�c�́A�~�c�͓�A�����K���A���[��Y�A�g���F���Y�e�ٌ�m�Ɠ��E�ł���B�j
|