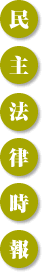 |
 |
 |
- 事件の概要
本件は、大阪を本拠とするオーケストラである大阪シンフォニカー交響楽団において生じた不当労働行為事案である。
申立人は、平成元年、大阪シンフォニカー交響楽団に入団し、その音楽性が評価されて平成6年にはティンパニーを含む打楽器部門の首席奏者となった。その後、平成14年に楽団員の労働条件の改善を求めるなどの活動を行う楽員会の会長に就任し、交通費の支給や病欠時の自己負担をなくすなどの要求を実現させたり、平成18年に楽団内の組合が結成されると、初代の副代表に就任したりするなど、楽団員の労働条件向上などを求める中心的な役割を果たしてきた。
これに対し、楽団側は、従前から「組合を結成するのはマイナスにつながる恐れの方が大きい」と明言するなど、組合活動について敵対的な態度に終始してきたところ、申立人が先述のような活動を行うのに対し、平成16年には音楽的能力に欠けるなどとして演奏機会の多いティンパニーの担当から外すという挙に出るとともに、労働問題ではないなどと強弁して、楽員会との交渉や申立人が加入した組合との団体交渉にも一切応じなかった。さらに、楽団内に組合が結成されると、申立人に対し、ゲネプロ(本番前の全体練習)に遅刻した、リハーサルの出番に不在だった、それらの報告書が未提出などとして、懲戒解雇をほのめかして退職勧奨し、これに申立人が応じないとみると、平成19年4月、申立人を打楽器部門首席奏者から一般奏者(トゥッティ)に降格した。
申立人と組合は、この降格が不当労働行為であるとして、大阪府労働委員会に救済申立をした。
- 審理の状況
楽団側は、当初より、労働条件の改善を求める楽団員の活動に対して嫌悪感を示し、楽団員からの要望をほとんど受け入れないばかりか、検討する態度さえも見せていなかった。そのため、楽団側の、楽団員による組合活動に対する否定的態度は明らかであり、弁護団としては、負けるわけにはいかない事件であった。
これに対し、楽団側は、従来挙げていた降格理由に加え、申立人が首席奏者としての適格に欠けるなどとして、申立人の個人攻撃を行ってきた。
- 府労委命令の内容
大阪府労働委員会は、8人にも及ぶ証人尋問を経て明らかになった事実関係を丁寧に認定し、まず、首席奏者からトゥッティへの降格処分は、首席奏者手当を支給されなくなるとともに、首席奏者が担当する重要なパートを演奏できなくなる、パートのリーダーとしての権限がなくなる、音楽家としての評価が低下するなどの重大な不利益取り扱いであるとした上で、遅刻等があったとしても、それは譴責や重くとも出演停止等に該当しうるに止まるのであって降格の必要性は認められないこと、今まで首席奏者に非違行為があっても首席奏者からトゥッティに降格したことはなかったことから降格処分に相当性は認められないとした。そして、申立人が、組合活動などにおいて楽団員の中心的な役割を果たしてきたこと、申立人及び組合と、楽団側との間で申立人や楽団員の処遇や評価を巡り対立関係にあったこと、楽団側が労働組合の結成を快く思っていなかったことが認められるとして、申立人に対する降格処分は、組合が楽団員の待遇改善などの要求を一層強めることを危惧した楽団側が、申立人が組合員であることを嫌悪してなされた不利益取り扱いであり、組合の弱体化を企図してなされた支配介入行為であって、不当労働行為にあたると断定した(平成21年1月27日命令)。
- 命令の意義
オーケストラの楽団員は、才能に恵まれ、幼少のころから特別の訓練を重ねた一握りの人しかなることができない。そしてそのすばらしい演奏で、聴く者に対し、他では得難い感動を与える。
しかし、日本におけるオーケストラの楽団員の処遇は、極めて劣悪な環境にある。また、楽団側と各楽団員との関係は、前近代的な労使関係にとどまり、楽団員は個別分断されて、低い労働条件を強いられてきた傾向にある。大阪シンフォニカーにおいても、楽団側の恣意的な意思決定によって、楽団員の地位や処遇は常々脅かされてきた。
今回、大阪府労働委員会が、楽団側の組合に対する嫌悪の体質を糾弾し、楽団員に対する不当労働行為を認定したことは、本件事案に即してみれば当然のこととはいえ、楽団員の地位向上や、労働条件の改善に向けた動きに、大きな意味を持つものと言えるであろう。
今回の大阪府労働委員会の命令に対しては、楽団側が再審査を申し立てたため、今後も中央労働委員会にて審理が継続し、解決にはまだ時間がかかることになった。文化の担い手に対する環境が悪化する現状の中(楽団そのものの存亡も危ぶまれている楽団さえ存在する。)、守られるべき権利が守られるよう、引き続き努力したい。
- (弁護団は、梅田章二、小林徹也、生越照幸、今春博)
- 平成21年3月5日、過労死家族の会の寺西笑子さんを請求人として、大阪過労死問題連絡会のメンバーによって大阪労働局に対して2つの情報公開請求を行った。
1つは、①過労死・過労自殺を生じさせた企業名の公開を求めるもので、もう1つは、②是正勧告を行った事案の公開を求めるものである。
当初、①については、「大阪府内に本社を置く下記企業につき、大阪労働局管内の各労働基準監督署長が平成14年4月1日から同21年3月5日までの間に、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)に係る労災補償給付の支給請求に対して支給決定を下した事案につき、その処理状況を把握するために作成している処理経過簿のうち、被災者が所属していた事業場名(法人名のみ)、労災補償給付の支給決定年月日」を対象として、大阪府内に本社を置く企業のうち、従業員数が1万人を超える企業を具体的にその企業名を列挙して請求していたが、請求に行った際に、情報管理専門官から、当該請求が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第8条の「存否応答拒否」に該当して公開できない可能性がある旨の指摘を受けた。
そこで、上記具体的企業名を挙げての請求から、「従業員数1万人以上の企業」という内容に変更して請求することになった。
また、②については、「大阪労働局が保管している、大阪中央労働基準監督署長が平成15年4月1日から同21年3月5日までの間に、同労働基準監督署管内の事業場に対して労働基準法及び労働安全衛生法違反について是正勧告を行った事案についての是正勧告書並びに是正報告書」を対象としてその公開を求めたが、是正報告書の別添資料が膨大な量になってしまう旨の指摘を受けた。
そこで、是正勧告の時点で従業員数が1万人以上の企業に対する是正勧告に限定し、かつ、期間も平成18年度・19年度の2年度分に限定する形に変更して請求することになった。
これらの請求は、過労死事件で労災認定を得て、更に損害賠償請求訴訟で勝訴しても、過労死・過労自殺を生み出した企業の体質自体には何らの変化もなく、過労死・過労自殺を生み出したことに対する認識を改めることも反省することも見られないという現状のままでは、企業に真に過労死・過労自殺を生じさせたことの責任を理解させることができているとは言えず、過労死・過労自殺はいつまでたってもなくならないという現状を打破すべく行ったものである。
企業に真に自らの責任を理解させるためには、損害賠償によって経済的制裁を与えるだけでは不十分である。当該企業において過労死・過労自殺が生じたということや長時間労働が常態化した劣悪な労働環境下に労働者をおいているということが白日の下にさらされることで社会からの痛烈な批判を受けるのでなければ、企業が自らの責任を真に理解し、労働時間管理等の再発防止策を講じることは期待できないのである。
したがって、なんとしてでもこれらの情報の公開を受けて、過労死・過労自殺を生じさせ、若しくは生じさせるおそれのある労働環境下で労働者を働かせている企業を社会の批判の下にさらすべく、本件請求によって各情報の公開を受けられなかった場合には、最終的には情報公開訴訟を提起する予定である。
この活動は、松丸正弁護士による問題提起を受けて、立野嘉英弁護士に積極的に動いていただく形で実現したものである。本来であれば、私も立野弁護士と共に動き回る役回りを仰せつかっていたにもかかわらず、立野弁護士の素早い対応に甘えて任せっきりになってしまったことをただただ反省するばかりである。情報公開訴訟に至った際には、私も他のメンバーと共に過労死・過労自殺のない社会の実現に向けた更なる一歩を歩み出すため、本気で訴訟に取り組むことを決意して本件報告を終える。
- 遣切りが止まらない
2008年秋以降、経済危機を理由にした派遣契約の解除、期間雇用労働者の解雇が増大している。1月に発表された厚労省の調査では3月末までに契約解除となる派遣労働者は約15万人とも言われ、人材派遣協会の調査では40万人とも言われている。こうした中、年度末になる3月末まで派遣切り等となる労働者の相談や契約解除や解雇となり生活の場を奪われた労働者のために日弁連でも非正規派遣切りホットラインを3月9日午前10時から実施する取組にあわせて一斉提訴を計画した。
全国の労働弁護団員に呼びかけて、3月6日で偽装請負や違法派遣で就労先の雇用責任を問う一斉提訴を計画したところ、6日と9日の2日にかけて大阪地裁、神戸地裁姫路支部、名古屋地裁、福井地裁の4つの裁判所に提訴することが出来た。
- 違法派遣(偽装請負)先の直接雇用を「推奨する」厚労省通達の発令
厚労省は昨年11月28日に厚生労働省職業安定局長通達(職発1128002号)を発し、製造業や違法派遣などで派遣制限期間を超えている場合などには、契約を解除するにあたり、当該労働者の雇用の安定をはかる措置をとることを前提にせよという従来の指導に加えて、派遣先(偽装請負の場合は発注先)に対し、直接雇用を「推奨する」よう徹底せよとの通達を発し、行政の指導においても派遣先の雇用責任を求める姿勢を示した。
こうして厚労省自身が従前の指導に加え、派遣先責任を積極的に求める方針転換を示したこともあり、今回のホットラインで、違法派遣(偽装請負)状態であった場合は、労働局への申告を位置づけ直接雇用を求める取り組みを呼びかけた。
- 訴訟による就労先の責任追及の意味
上記の労働局の指導は、現行派遣法上の救済規定に基づくものではなく、あくまで行政の裁量による指導であり、その救済手段には限界がある。
違法状態で長年にわたって稼働してきた派遣労働者は、改めて自分たちがどんなに頑張っていても企業にとっては調整弁としての都合のよい就労形態であることを知り愕然とすると共に、本来であれば直接雇用されて然るべきであるのに違法行為を重ねてこうした雇用責任を回避していることに気づいたこともあり、当事者らは厚労省通達よりさらに一歩進んで、裁判による派遣先責任追及に立ちあがりはじめた。
- 黙示の労働契約論に基づく裁判闘争への発展
偽装請負ないし違法派遣に関しては、先の通達が発せられる前である2008年4月26日、松下プラズマディスプレイ(現パナソニックプラズマディスプレイ)に対する就労先との雇用契約関係を認定した大阪高等裁判所判決がある。
大阪高裁判決は、労働者と偽装請負をしていた会社(違法派遣元会社)と労働者との間の契約は、「雇用契約」とは言えないか、「雇用契約」でも労働者供給を禁じた職業安定法に反して、それは公序に反するから民法90条によって無効であるとして、請負会社(派遣元)と労働者の雇用関係を否定し、指揮命令関係、労務提供関係、賃金支払い関係は派遣先の間にあると認定して、違法な派遣状態で指揮命令をしていた派遣先会社と労働者の労働契約関係があるとの判断を示したものである。
そして、偽装請負や違法派遣で長期雇用が継続している労働者が雇用責任を追及するには、この大阪高裁の論理を発展させ、多数の事例で就労先の雇用責任を認める判決を勝ち取ることがもとめられている。
- 4つの事件の共通点
(1) 3月6日に提訴した事件は、①福井地裁に提訴したパナソニック若狭事件、②神戸地裁姫路支部に提訴した日本化薬株式会社事件である。
いずれの事件も、もともと職場において当事者が就労した時は派遣ではなく、偽装請負状態での就労が開始されており、先の松下PDP事件の判断を当てはめれば当初は労働者供給であり、形式上の雇用主との間に労働契約関係があるとは言い難く、就労先との間に黙示の労働契約関係の成立を認められてしかるべき事案である。
日本化薬は3年半以上も就労を継続してきた事案であり、またパナソニック若狭も4年にわたって社員と一緒の労働に従事してきた事案であり、期間の点からも就労実態からも松下PDP事件の場合に勝るとも劣らない偽装請負事案である。
特に、パナソニック若狭は、松下PDPなどで指摘された違法派遣により労働局から松下が受けた指導内容が生かされることもなく、地方とはいえ違法行為を繰り返してきた事例であり、国会で日本共産党が取り上げてその違法性がただされた経緯もある事案である。
(2) 3月9日提訴分は、③名古屋地裁に提訴した三菱電機事件と④大阪地裁に提訴したセキスイハウス事件である。
名古屋地裁は、7年前から就労している男性労働者ら3名であり、偽装請負状態から派遣契約に切り替えられ、その後に派遣切りにあった事案である。期間の点では2002年から始まった就労であり、偽装請負状態での就労が早期から始まり長期的に続いていたことを示している。他の訴訟と同様、黙示の労働契約の成立を主張している。
大阪地裁に提訴したセキスイハウス事件は、派遣元のリクルートスタッフィングも被告に加えているが、偽装請負ではなく、派遣就労の制限期間のない政令指定業務として契約をしながら、その実態は、一般事務の労働者派遣の業務を5年近くもさせていたという事案である。
一旦契約を終了させられたが、その際、改めて派遣として来てもらうという言葉を信じ、雇用保険の手続きもせずに待っていた女性労働者は一方的に再復帰はなくなったと通告された。この場合も就労可能期間を越えて違法に派遣受入をしてきたものであって違法な派遣状態で3年以上も就労をしていたものである。
この場合でも、違法派遣の派遣先は派遣法上の義務を免れるために業務をごまかして派遣契約を締結していたものであり、脱法的に雇用主責任を回避して指揮命令をしていたという点では、偽装請負事案と同様に派遣先の雇用責任が認められるべき事案である。
以上のとおり、上記①から④の事件は、いずれも派遣先(請負就労先)に対して、直接の雇用契約関係の確認を求める請求をしたのである。
派遣労働者が安易に契約解除をされる中、行政でさえ派遣先責任を求める踏み込んだ指導している中、当事者が立ちあがり、派遣先に対して雇用責任を追求する訴えを起こし始めたのである。
当事者が立ち上がったことはホットライン実施と共に大きく報道された。当事者が立ち上がり、労働組合に加入し、さらに裁判闘争を闘うまでに至ったことは、雇用喪失に悩む労働者を励ますことになったと確信する。
日弁連のホットラインでは、大阪が全国でもっとも多かったことはこうした報道と無縁ではないと思う。始まった当事者の闘いに多くの支援を寄せていただきたい。
|