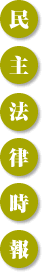 |
 |
 |
- ���Ă̊T�v
(1) ���ʖ{�̂ւ̈ڐ�
�@�����̂e����3���́A���Ɠ��ʗ���^�A�Ƃ������ʂ̎q��ЂŃy���J���ւ̔z�B�Ɩ��ɏ]�����Ă����B
�@1999�N�H�A2000�N4���������ăy���J���Ɩ�����ʖ{�̂Ɉڂ����j��������A��������܂ޏ]�ƈ������ʖ{�̂ւ̈ڐЂ����߂�ꂽ�B����^�A�̘J�g�ψ����ł������e�����2000�N3���̏t���Ì���A�S���ʖ����y�щ�Б����A�u�ڐЂɓ������Ă͎q��Ђł̋��^������ۏႷ��A�ꎞ�����ۏႷ��A�ސE���͂Ȃ��Ȃ邪�A�����ł�������Ɍ��������^����B�S���ʂɂ͈ڐЂ�1�N��ɉ���������v�Ƃ̐��������B
�@���ʗ���^�A�̎В��j����������܂ޏ]�ƈ��ɑS�����l�̐����������B����ɂ��̌���ʖ{�̂̊��y���J���E�A���[�x�X�̑����ے�������^�A��K��A��������܂ޏ]�ƈ��ɑ��A�O�L���l�u�q��Ђł̋��^������ۏႷ��A�ꎞ�����ۏႷ��A�A���ސE���͂Ȃ��Ȃ�v�Ƃ����������J��Ԃ����B
�@������͂����M�p���A���ʂƂ́u�ٗp�_�v�i�����ɂ��āu�x�X�Ј������K��ɂ��v�Ƃ̋L�ڂ�����j�ɏ����E�����B�@
(2) �ڐЌ�̒����_�E��
�@�Ƃ��낪�A���ۂɂ͈ڐЂƓ����Ɍ�����̒����͎q��Ў���̋��^������85�`95���ɃJ�b�g����Ă����B�܂����^�̌n�͂���܂ł́u��{���{�蓖�v������������ɕύX����A���̌�2000�N6��2���y��2001�N1��26����2�x�̒����K��̉���(�^���������L�����ǂ��������Ɏ���܂ŕs��)�ɂ������̍Œ�⏞�z�̏����艺����ꂽ�B
�@�܂��A�]�O�̈ꎞ���͕ۏႳ�ꂸ�A���X�ɒ�z�̃C���Z���e�B�u�̎x���ƂȂ�A�x���[���̎����������B
(3) �S���ʘJ�g�̔w�M
�@������͎q��Ђ̏]�ƈ��ł��������A�g���͓��ʖ{�̂̑g���i�S���ʁj�̎P���ł���S���ʘJ�g���싦�c��ɏ������Ă����Ƃ���A�ڐЂ̘b���o�Ă��鐔�����O�ɁA�S���ʂ��˔@�Ƃ��Ďq��ЂœƎ��ɑg�������悤�����n����A�e�����̈ψ����ƂȂ����B�����ĈڐИb���o�Ă����Ƃ��̓��ʗ���^�A�̎В��j�́A�J�g�̗��싦�c���̈ψ����ł���A�e����͑g�������̐�y�ł���j��M�p���Ă����B
�@�Ƃ��낪�O�q�̒ʂ�A�ڐЌ�ɒ������J�b�g���ꂽ���߁A������͑S���ʂɏ��������߂��B�������A�ڐЎ��̏����Ƃ��ĈڐЌ�1�N�����Ȃ��ƑS���ʂɉ����ł��Ȃ����ƂƂ���Ă������߁A�S���ʂ́u�N�����͂܂��g�����ł͂Ȃ��v�Ƃ��Č�����̑i�������グ�Ȃ������B
�@�������2001�N4���ɂ͑S���ʂɉ����ł��A��Ђ̕s���Ȓ����J�b�g�����ɗ͂�݂��Ă��炦����̂Ɗ��҂��Ă����B�������A�S���ʂ͉��̐������Ȃ��܂܌�����̑g���������������A���̈���ŁA2001�N8��23���A�S���ʂ͉�ЂƂ̊ԂŁA�u��̓I�ɂ͕ʂɒ�߂�v�Ƃ��������Ŏ�����O�q�̒����J�b�g��ǔF������e�̘J�������������A�����2002�N3��31���A�����_�E���E�ꎞ���s�x����ǔF����J�g���肪���ʑ��x�X�ƑS���ʘJ�g���x���̊ԂŒ������ꂽ�B�����炪�S���ʂւ̉�����F�߂�ꂽ�̂�2001�N9��1���̂��Ƃł���B
- ��i�Ɣ퍐�̉��i�ԓx
(1) ��i
�@������͑g��������~�ς����ۂ���A��ނȂ��q��Ў���̋��^�E�ꎞ���ƌ��݂̋��^�E�ꎞ���Ƃ̍��z�����߂Ė{���i�ׂɓ��ݐ������A��L�̂悤�Ȏ���͒�i��̋��ߖ��ɂ���ď��߂Ė��炩�ɂȂ������̂ł���B�ŏ��͂Ȃ����������̒������������Ă���̂��S��������Ȃ��܂܂ɁA��T���Ԃł̒�i�ł������B
(2) �퍐�̉��i�ԓx
�@����ɑ��A�퍐�́u�ڐЎ��Ɏq��Ђł̋��^�����̈ێ�����������͂Ȃ��v�Ƃ����۔F�ɏI�n���A�ٔ����́u�퍐�Ƃ��Ĕ۔F�ȊO�ɁA��̓I�ȃX�g�[���[�̎咣�͂Ȃ��̂��v�Ƃ̜ϜȂɂ��u�۔F�ȊO�̐ϋɓI�咣�͂��Ȃ��v�Ƃ̑ԓx���Ƃ����B
- ����
(1) �{���̎傽�鑈�_�́A�@�ڐЂ̍ۂɏ]�O�̒����z�E�ꎞ����ۏႷ������������A�A2�x�̒����K������̌��́A�B2002�N3��31���t�J������̌��́A�C�������p���̗��p�̗L���ł���B
(2) �ڐЂ̍ۂ̕ۏ�̗L���ɂ���
�@���̓_�ɂ��A�����̎咣�𗠕t���鏑�͂قƂ�ǂȂ��Ƃ����Ă悢�ł��������A����ł��ٔ����́A���̂悤�Ș_���ŕۏ�̑��݂�F�肵���B
�@�u������́A���i�̊�]���������킯�ł��Ȃ��̂ɁA�퍐�̉c�ƕ��j��̗��R����퍐�ւ̈ڐЂ����߂��Ă������̂ł���B����ɂ�������炸�A�����̒ቺ�A��Ɉꎞ���̋��z���s�m��ƂȂ邱�Ƃ������܂��ڐЌ�̒����̌n���ݒ肳��Ă���퍐�ւ̈ڐЂɂ��āA�����炪����ًc���q�ׂ���R�c�����Ȃ������Ƃ����̂́A�i�ʂ̗��R������������ł���ƍl������Ȃ��B�v
�@�u�����ł�����i�ʂ̗��R�ɂ��Č�������ɁA������́A����^�A�ɂ���������z��ۏႷ��|�퍐�������Ƃ̋��q�́A�i�ʂ̗��R�Ƃ��č����I�����R�ł���A�M�p�ł���B�v�Ƃ��A����ɔ퍐�ɂ͌�������ڐЌ�̋Ɩ��ɐϋɓI�Ɋ��p����ړI�����������Ƃ��w�E���āu�������퍐�̉��ɗU���ׂ��A�ϋɓI�ɔ퍐���D����������\�����ے�ł��Ȃ��Ƃ���ł���v�Ƃ����B
�@�܂��A�ꎞ���ɂ��Ă��A�u�����̑傫�ȕ������߂Ă����ꎞ���ɂ��A�����炪����퍐�Ɩ��邱�ƂȂ��A�퍐�ƌٗp�_�����������ƍl���邱�Ƃ͍���ł���v�Ƃ��āA����^�A�œ��Ă����ꎞ����8�����Œ���x�x�������Ƃ����ӂ���Ă����Ƃ����B
(3) �����K������̌��͂ɂ���
�@2�x�̒����K��������A�ƋK���̕s���v�ύX�ɂ�����ƔF�肵����ŁA�A�ƋK���̕s���v�ύX�ɂ������ẮA�u�A�ƋK���̕ύX�ɂ��J���҂���邱�ƂɂȂ�s���v�̒��x���l�����Ă��A�Ȃ����Y�J�g�W�ɂ����铖�Y�����̖@�I�K�͐��F���邱�Ƃ��ł��邾���̍������v���K�v�ł���A���Ƃɒ����ɂ��Ắu���̂悤�ȕs���v��J���҂ɖ@�I�Ɏ�E�����邱�Ƃ����e���邱�Ƃ��ł��邾���̍��x�̕K�v���Ɋ�Â��������I�ȓ��e�̂��́v�ł��邱�Ƃ��K�v�ł���A�{���ł͑�z���Ƃł͐Ԏ����o�Ă����Ƃ��Ă��퍐�S�̂Ƃ��Ă͘J���g�������グ��v�����邱�Ƃ���������ł���A�������������̕K�v���͂Ȃ������ƔF�肵���B�܂��A�����K�����ɂ��ĘJ���g���̈ӌ��悵�Ă��Ȃ����Ƃ����R�Ƃ��Ă���B
(4) �J������̌��͂ɂ���
�@�O�q�̒ʂ�A�����炪�S���ʂɑ��ĈڐЎ��̖����悤�v�����Ă�����ł���ɂ�������炸�A�]�O�̌�����̍Œ�ۏዋ�����z������e�̘J�����������ꂽ���̂ł��邪�A�����́u�J���҂̒n�ʂ̌����ړI�Ƃ���J���g���������鍇�ӂ��Ȃ��Ƃ͗e�Ղɍl�����Ȃ��Ƃ���ł���A�����I�ɉ��߂���A��L�J������́A������̒����ɂ��ĕ�������������ŁA���ʁA�퍐���Œ���x�����ׂ����z���߂����̂ɉ߂����A������̒����ɂ��Ă̖@�I�Ȋm��́A���̌�̊W�҂̌��◚�H����@�I�葱�Ɉς˂����̂ƔF�߂�ׂ��ł���v�Ƃ����B
(5) �������p���̗��p�ɂ���
�@�����A�������p���̗��p�ɂ��Ă͍ٔ����̔F�߂�Ƃ���Ƃ͂Ȃ�Ȃ������B
- �Ō��
�@�{�������́A�ڐЎ��̌����ł̒����̕ۏ��F�߂��_�ō����]���ł�����̂ł���B
�@�܂������J���҂ɕs���v�ȘJ������̌��͂ɂ��āA�퍐���x�����ׂ��Œ���x���߂����̂ł���ƌ���I�ɉ��߂����_�ʼn���I�Ȃ��̂ł���B
�@�퍐�ł�����ʂ͔�����܂��Ȃ��T�i�����̂ŁA������T�i�R�œ����͌p�����邱�ƂɂȂ����B��R��������ނ����邱�Ƃ̂Ȃ��悤�����������B
- ���Ă̊T�v
�@�{���́A�S��F�����i����ȁE�������j���A���N�ɂ킽���Č��q�͔��d���ɂ����Ĕ�j���ɏ]�����đ����ʂ̕��ː��픘���A���̌��ʁA���������p��ɜ늳���Ď��S�������Ăł���B
�@������̍Ȃł��閖�q����i���ꌧ�ݏZ�j����̘J�А\���ɂ��āA����J����ē����́A�Q�O�O�U�N�X���S���A�u���a�̔��nj������s���Ɣ��f����邽�߁A���S�ƋƖ��Ƃ̑������ʊW���F�߂��Ȃ��v�Ƃ��āA�ی����t�s�x��������s�����B���̌�����́A������̜늳�������������p��A�J���Ȋ��W�P�O���u�d�����ː��ɌW�鎾�a�̋Ɩ���O�̔F���ɂ����āv�i�ȉ��u��W�P�O���v�Ƃ����B�j�ɑΏێ��a�Ƃ��Čf�����Ă��Ȃ����Ƃ𗝗R�ɋɂ߂Č`���I�ɂȂ��ꂽ���̂ł���A������ȑO�Ɍ����J���Ȗ{�Ȃւ̂��f�����{����Ȃ������B
�@�������Ȃ���A�����a�ł���A��W�P�O���ɂ����đΏێ��a�Ɏw�肳��Ă���Ƃ���A���������p��́A��ɏq�ׂ�悤�ɁA�����a�̗މ������ł������łȂ��A�픘�ɂ�鈫�������p��ǂ̃��X�N�ɂ��ẮA���Ɋe���ʂ���w�E����Ă����B���̏�A������̔픘�ʂ͌����J���҂̒��ł��ɂ߂đ����A���ɐ�����̎��a�������a�ł���A��W�P�O���̔��f��ɂ���ē��R�ɋƖ��N����������A�Ɩ��㎾�a�Ƃ��ĔF�肳��邾���̑����ʂ̔픘�����Ă����B
�@�����ŕٌ�c�ł́A���̌�����ɑ��ĐR����������Ƌ��ɁA�����J���Ȗ{�Ȃւ̂��f��������ׂ��A��w�I�ȓ_�𒆐S�Ɏ咣���������邱�ƂɂȂ����B
- ���������p��Ɣ����a�̗މ�������
�@���������p��Ƃ́A�������̒��̃����p������������ᇂł���A�����p�߂���ꂽ��A��ᎂ������鎾�a�ł���B�����A�����a�Ƃ́A�������ɂ����Ė��n�Ȕ��������ˑR�ψقɂ�萳��ɐ����ł��Ȃ��Ȃ�A�܂��ُ�ɑ��B����a�ςł���B���̂悤�ɁA���҂͂���������t�i�������j�̂���A���Ȃ킿�������ᇂł���Ƃ����_�ŋ��ʂ��Ă���i�����ł���������́u��ᇁv�Ƃ́A�Ō`����ɂ�����悤�Ȉُ�זE�̉����邱�Ƃ��Ӗ����Ă���̂ł͂Ȃ��A�זE���������ɑ��B���邱�Ƃ��w���Ă���j�B
�@���Ƃ��ƁA�������זE�́A�͂��߂ɍ����n���זE�ƃ����p�n���זE�ɕ������A���̌ナ���p�n���זE�����n���Ăs�זE�A�a�זE�A�m�j�זE���ɕ������Ă����B�����āA���̕����E���n�ߒ��̂�����̒i�K�ł����N����\��������A���̂��߁A���t�̂���ɂ͎��ɑ����̎�ނ�����B
�����āA���n�ȃ����p���̒i�K�ł̎�ᇂ͔����a�̌`���Ƃ�A���n���������p���̒i�K�ł̎�ᇂ͈��������p��̌`���Ƃ�̂ł���B
�@���̂悤�ɁA���������p��Ɣ����a���r����ƁA��������������ُ̈푝�B�i����j�Ƃ����_�ł͋��ʂ��Ă���̂ł���A�����A�ُ푝�B����̂��A���n���ٌ͈`�̔��������i�����a�j�A���@�\���P��̐��n�������������i���������p��j�Ƃ������Ƃɉ߂��Ȃ��̂ł���B
�@���̂悤�ȗ��҂̗މ��������́A�v�g�n�i���E�ی��@�ցj�ł��F�m�����Ɏ����Ă���B
�����ł���ȏ�A�����a�݂̂���W�P�O���őΏێ��a�Ƃ���A���������p����O����A�J�ДF������̊�W�P�O���̌`���I�^�p�ɂ���ĂȂ���Ă��錻��͖��炩�ɕs���Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
- �픘�ƈ��������p��Ƃ̈��ʊW
�@�픘�ƈ��������p��Ƃ̈��ʊW�ɂ��ẮA����܂Ŋe��̉u�w�������Ȃ���Ă���A�픘�ɂ���Ĉ��������p��ǂ̃��X�N���L�ӂɑ������邱�Ƃ�����Ă���B�A�����J�ł́A���ː��픘�ޖ��R�l�⏞�@���A���������p���⏞�Ώێ��a�Ɏw�肵�Ă���B
�@���{�̌����J���҂̒��ł����������p��Ŏ��S�����l�́A���łɂW�P������A���݂́A���炩�ɂȂ��Ă͂��Ȃ����A����̍����ʔ픘�Q�ł̎��S�҂̔����ɂ���ẮA���ʈˑ��W�����ĂɂȂ�\��������B
�@���̂ق��A���q�͔��d���t�߂̏Z���Ɉ��������p��������Ă���Ƃ̕�����i���Ώ���Y�u�m���������p��n�����n�т̋��|�v�j�B
�@���̂悤�ɁA�����a�މ������ł��鈫�������p��ɂ��Ă��A���ː��픘�Ƃ̈��ʊW�͊��ɉu�w�I�ɖ��炩�ɂ���Ă���A�ƌ����Ă悢�ł������B
- ������̘J�����ԂƔ픘����
�@������́A�P�X�X�V�N�W���A���q�͔��d�����ɂ������j���Ɩ�����Ƃ���T���G�b�N�X�R�[�|���[�V�����L����Ђɓ������A�Q�O�O�S�N�P���Q�O���ɑ̒��s�ǂ̂��ߑސE����܂ʼnғ������B
�@��j���́A�@���z�ǂ̓����̏�Ԃ��G�b�N�X���̓��ߎʐ^�ɂ�蔻�f������ː����ߌ������͂��߁A�����g�ɂ��[�������⌸���E���H�̒��x��c�������������ȂǁA�H�ƕ���ɂ����čL�����p����Ă��邪�A���ː��@����g�����߁A�E�Ɣ픘�̕���ł́A�픘�ʂ̑����E��̈�ł���B����ɁA���q�͎{�݂ł́A��ƌ���̕��ː������ɂ��픘�������B
�@������́A��Ɍ��q�͔��d���̒�������ŕ��˔\�R�����������Ɩ��Ɍg����Ă����B�P�X�X�V�N�X���Q���ɏ��߂Ėk�C���d�͔����q�͔��d���̒��������Ƃɓ����Ĉȍ~�ސE����܂ł̖�U�N�S�����ԁA�S���e�n�̌��q�͔��d���Ŏd�������Ă���A�Q�O�O�O�N�P���̏H�c�Η͔��d���ł̕��ː��B�e��Ƃ������A����������q�͔��d���y�эď����H��ł���A�픘����Ə�ł������B
�@������̊O���픘�W�ϐ��ʂ́A�ȉ��̂Ƃ���A�ғ������U�N�S�����̊ԂłX�X�D�V�U�~���V�[�x���g�ɂ��y��ł����B
�@�@�P�X�X�V�N�x�@�@�U�D�R�O �~���V�[�x���g
�@�@�P�X�X�W�N�x�@�P�R�D�O�O �~���V�[�x���g
�@�@�P�X�X�X�N�x�@�P�P�D�P�O �~���V�[�x���g
�@�@�Q�O�O�O�N�x�@�P�V�D�R�R �~���V�[�x���g
�@�@�Q�O�O�P�N�x�@�P�V�D�W�O �~���V�[�x���g
�@�@�Q�O�O�Q�N�x�@�P�W�D�Q�W �~���V�[�x���g
�@�@�Q�O�O�R�N�x�@�P�T�D�X�T �~���V�[�x���g
�@�Ȃ��A���ː��]�ƎҒ����o�^�Z���^�[�̔��\�ɂ��A���ː��Ɩ��]���҂̔N�ԕ��ϔ픘���ː��ʂ͈ȉ��̂Ƃ���ł��邪�A����ƑΔ䂵�Ă݂�ƁA������̔픘���ʂ������I�ɋɂ߂č����������Ƃ�������B
�@�@�P�X�X�V�N�x�@�@�P�D�R�@�~���V�[�x���g
�@�@�P�X�X�W�N�x�@�@�P�D�Q�@�~���V�[�x���g
�@�@�P�X�X�X�N�x�@�@�P�D�R�@�~���V�[�x���g
�@�@�Q�O�O�O�N�x�@�@�P�D�R�@�~���V�[�x���g
�@�@�Q�O�O�P�N�x�@�@�P�D�R�@�~���V�[�x���g
�@�@�Q�O�O�Q�N�x�@�@�P�D�S�@�~���V�[�x���g
�@�@�Q�O�O�R�N�x�@�@�P�D�U�@�~���V�[�x���g
�@��ɂ��G�ꂽ��W�P�O���́A�T�~���V�[�x���g�ɉғ��N�����悶���l�ȏ�̔픘�������҂��A�픘�J�n��P�N�ȏ��ɔ����a�ǂ����ꍇ�ɂ́A�Ɩ��ɋN��������̂ƔF�߂�Ƃ̊�������Ă���B
�@����ɑ��A������̔픘�ʂ́A�U�N�S�����ԂłX�X�D�V�U�~���V�[�x���g�ł��邩��A��W�P�O���̔����a�ɂ��Ă̊�l��ꡂ��ɏ���B���Ȃ킿�A������́A�������������p��ł͂Ȃ������a�ɜ늳���Ă����Ȃ�A���R�ɋƖ��N�������m�肳��邾���̐[���ȕ��ː��ʂɎN����Ă����̂ł���B
- �@�{���́A��쒆���a�@�̑��c�O�Y��t�ɂ��d���Ȉӌ������͂��߁A�x���c�̂ɂ��̐��͓I�Ȍ����J���ȂƂ̌��Ȃǂ̊������t�����āA�����J���Ȗ{�Ȗ{�ȂŌ�������d�˂����ʁA���ʂ̘J�ДF��ƂȂ����B
�@�{���J�ДF�肪�A�ł̒��ƌ����邱�Ƃ����������J���̎��ԉ𖾂ɖ𗧂��Ƃ��肤����ł���B
�@�Ȃ��A�ٌ�c�́A�����]�i����j�A�c���䂩��i���j�A���؋g�N�i���j�̂R���ł���B
|