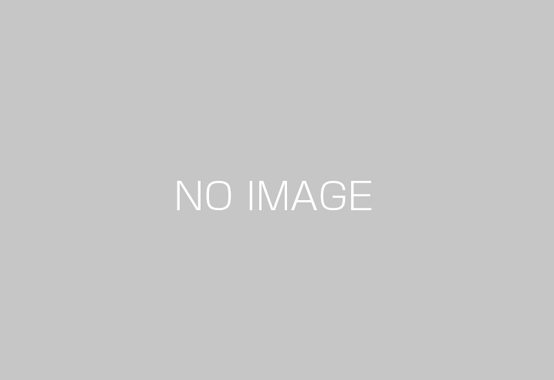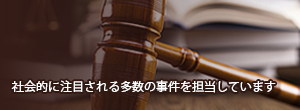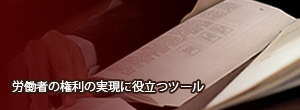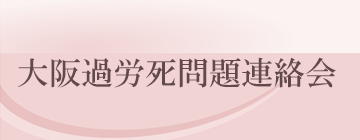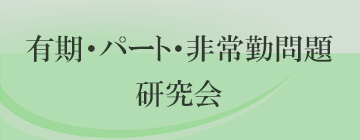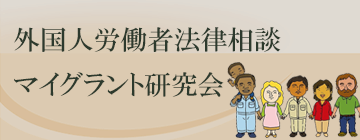弁護士 中西 基
1 はじめに
大阪大学の非常勤講師らが労働契約法18条の無期転換を主張して地位確認等を求めていた訴訟について、2025年1月30日、大阪地裁(第5民事部・横田昌紀、蒲田裕一、山中洋美)は、原告らの請求を棄却する判決を言い渡した。本訴訟の争点は、原告ら大学の非常勤講師が、労働契約法上の労働者に当たるかどうかであった。大阪地裁判決は、原告らは労働者ではないとして、労契法の適用を否定したが、この理屈によるならば、全国どこの大学の非常勤講師であっても、労働者ではないということになってしまう。あまりにも社会の現実から乖離した非常識きわまりない不当判決である。
2 事案の概要
大阪大学には1,000名以上の非常勤講師が勤務している。その多くは、本業や本務校のない、いわゆる「専業非常勤講師」である。賃金は1コマ(120分)あたり1万3,770円、月給にすると10~20万円程度にすぎない。生計のために複数の大学で非常勤講師を掛け持ちしているが、半年ないし1年の不安定な有期契約で働く非常勤講師らにとって、雇用の安定は切なる願いであった。原告らは、有期契約を更新して通算期間が5年を超えたことから、無期転換を申し込んだ。ところが、大阪大学は、非常勤講師との契約は「委嘱契約」であり、これは労働契約ではなく準委任契約であるから労働契約法18条の適用はないとして、無期転換を認めず、2023年3月末で期間満了を理由に雇止めにした。本件は、雇止めとなった非常勤講師らが原告となって、大阪大学に対して、無期契約労働者としての地位確認と賃金を請求する訴訟である。
3 大阪大学の取扱い
大阪大学は、2022年3月まで、非常勤講師は労働者ではないものとして取り扱ってきた。2007年10月に大阪外国語大学と大阪大学が統合して、大阪外国語大学の非常勤講師は、そのまま大阪大学でも非常勤講師として従前どおり勤務してきた。ところが、大阪外国語大学の時代は労働者であったのに、大阪大学に統合されてから以降は、勤務の実態は何も変わらないにもかかわらず、労働者ではないものとされた。その理屈は、非常勤講師との契約の形式は「委嘱契約」であり、その法的性質は労働契約ではなく準委任契約だからというものであった。原告らが加入する関西圏非常勤講師組合は、非常勤講師との契約が労働契約ではないとされることはおかしいと繰り返し追及し、国会でも問題であると取り上げられた。その結果、大阪大学は、2022年4月からは、非常勤講師との契約形式を労働契約に変更した。なお、契約形式は変更されたが、勤務の実態は従前とは何も変わっていない。
4 労働契約法上の労働者性
労働者であるか否は、労働法が適用される対象であるのかどうかの問題である。労働者でない者(=自営業者)には労働法の保護は与えられない。労働者か否かという問題は、労働法が生成された当初から、労働法の規制を免れるようとする使用者によって、繰り返し、繰り返し争われてきた。また、近年、デジタル社会の急速な進行とそれにともなう産業構造の変化により伝統的な労働者像にはあてはまらない多種多様な働き方が増えつつあり、例えば、プラットフォーム・ワーカーは労働者なのかどうか(労働法が適用されるのかどうか)が、あらためて議論となっている。労働者性の判断にあたって、もっとも重要なことは、契約当事者の主観を排斥して、客観的な就労・労務提供の実態から行われなければならないということである。これは、全世界で共通の、そして、歴史的にも確立された考え方である。
5 大阪地裁2025年1月30日判決
ところが、大阪地裁判決は、旧・大阪外国語大学時代と大阪大学統合後とを比べても、また、「委嘱契約」だった2022年3月までと労働契約となった2022年4月以降とを比べても、非常勤講師の就労の実態には何ら違いがないにもかかわらず、「委嘱契約」とされていた時期については、労働者ではなかったと判断した。原判決には数々の事実誤認がある。また、証拠から容易に認定できるはずの事実を認定しないところも多い。労働者性を否定するために恣意的な判断がなされているとしか思えない。また、大学の教員という働き方においては、授業の内容や遂行方法について、基本的に大学側から具体的に指揮命令されることは想定されない。このように具体的指揮命令になじまない業務について、原判決は、「その業務が本件各委嘱契約の内容に従って行われているにすぎないと評価し得るか、それとも、その業務にあらかじめ本件各委嘱契約において定めることが困難なものが含まれ、具体的場面において被告の指揮監督を想定する必要があるか」という観点から、労働者性を判断するという。具体的指揮命令になじまないはずなのに、具体的場面で指揮監督を想定する必要があるかどうかで判断するというのは、論理矛盾である。
特筆すべきは、この大阪地裁判決の判断枠組みは、2025年2月20日に東京地裁で言い渡された東京海洋大学事件とほぼ同じだということである。東京地裁判決は、「使用者の命令、依頼等によって通常予定されている業務以外の業務に従事することがある場合には一般的な指揮監督を受けていると評価され」るとしている。あらかじめ契約で定められておらず、予定もされていない業務について、それを履行する義務を負わないことは、契約である以上は当然のことであるはずだが、大阪地裁も東京地裁も、契約で定められていない業務を命じられても従わなければならないのが労働者であり、そうでない者は労働者ではない、としたのである。このような特異な判断枠組みを大阪地裁と東京地裁がほぼ同時に採用したということは、両裁判所において事前に判断内容についてすり合わせが行われていたことを強く推認させる。この点は、裁判の独立にもかかわる重大な問題であろう。
6 控訴審へ
原告らは直ちに控訴した。全国すべての大学の非常勤講師が労働者ではなく、労働法の保護を受けられなくなるという大阪地裁判決をこのまま野放しにするわけには行かない。控訴審での逆転にむけて原告団、弁護団ともに全力を尽くしたい。
(弁護団は、中村和雄、鎌田幸夫、冨田真平、喜久山大貴、中西基)