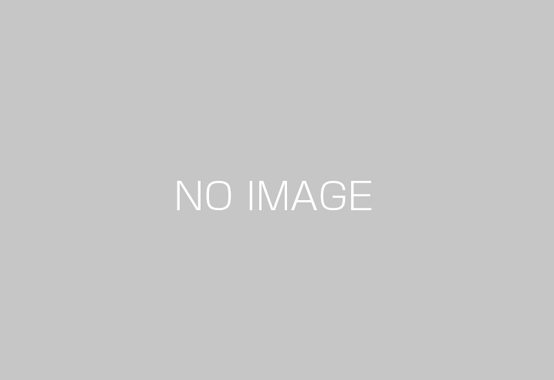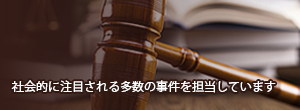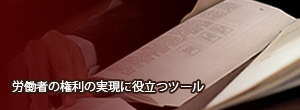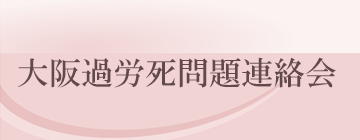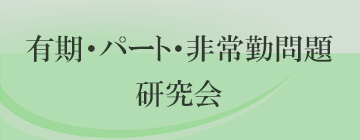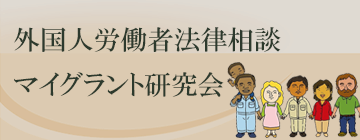弁護士 中村 和雄
■ 事件の概要
原告は、京都明徳学園が経営する成章高校に1年間の有期雇用契約である常勤講師として12年間社会科の教員として勤務していたのであるが、授業担当・校務担当・部活顧問などすべての教員業務において、無期教員である専任教員とほぼ同様であった。原告は2021年11月および2022年2月に無期労働契約転換を申し入れたところ、高校は同年4月から原告に対し教員業務を外し、図書館の整理業務担当へ配置転換した。ただし、賃金額は常勤講師の基準のままであった。また、同高校では、常勤講師と専任教員の賃金規定は別に定められており、常勤講師の賃金額は専任教員に比べて著しく低い。さらに、専任教員は毎年賃金額が増加するのに対して、常勤講師は勤続5年を超えると賃金額が増加しない規定となっている。しかも、無期転換した常勤講師は賃金額が増加しないだけでなく、有期契約のときには支給されていた期末手当が支給されない扱いとなっている。原告は、①配転の無効と②差別賃金の回復を求めて、2022年6月30日、京都地裁に提訴した。第1回口頭弁論期日は同年8月26日に開始し、16回目の裁判期日である。
■ 京都地裁判決の要旨
(1)配置転換について
結論 配転命令は有効 職種限定合意は認められない 権利濫用は認められない
理由 字数の関係で省略
(2)専任教員と常勤講師である原告との間の賃金格差について
判決は、「専任教員に支給される年齢給は、年齢によって定められる部分に加え、職務遂行能力に応じた職能給及び継続的な勤務等に対する功労報酬等の複合的な性質を有する」とし、 専任教員の年齢給及び常勤講師に支給される賃金(基本給)は、担当業務の相違によって左右される要素は乏しいものといえる。」とし、「少なくとも5年を超えて勤務する常勤講師については、専任教員と同様に、年齢によって定められる部分、職務遂行能力に応じた職能給及び継続的な勤務等に対する功労報酬を支払うという性質及び支給目的は妥当するものといえる。」として賃金格差は不合理であるとしました。さらに、判決は、原告の無期転換日以降について、「パート・有期法8条に違反するとはいえない。しかしながら、無期労働者である専任教職員と従前は有期労働者である常勤講師であった原告との間に不合理な賃金差があることに変わりはないから、同日以降も原告に専任教員よりも低い賃金しか支給しなかった被告の対応は原告に対する不法行為を構成する」と判示した。
■ 評価
1 判決が、配置転換の有効性に関し、原告と被告の労働契約について職種を教員職に限定する職種限定契約の成立を認定しなかったことは、極めて残念であり、高裁において立証を積み上げていきたい。一方、判決が無期の専任教員と有期の常勤講師との基本給における賃金格差について、労契法20条およびパート有期法8条の適用を認め、格差全額の損害賠償を認めたことは画期的である。名古屋自動車学校最高裁第3小法廷判決(令和2年10月13日・民集74巻7号1901頁)が基本給等の相違に関し、「他の労働条件の相違と同様に、当該使用者における基本給及び賞与の性質やこれらを支給することとされた目的を踏まえて同条所定の諸事情を考慮することにより、当該労働条件の相違が不合理と評価することができるものであるか否かを検討すべきものである」と判示したことから、専任教員の基本給(年齢給)の性質・目的と常勤講師の基本給の性質・目的をどう評価するかが問題となった。
そのうえで、原告のような「少なくとも5年を超えて勤務する常勤講師については、専任教員と同様に、年齢によって定められる部分、職務遂行能力に応じた職能給及び継続的な勤務等に対する功労報酬を支払うという性質及び支給目的は妥当するものといえる。」とした。長期雇用の常勤講師には、専任教員の年齢給の性質・目的が妥当するとしたのである。複雑な論理展開ではあるが、上記最高裁判決を踏まえ同判決の論旨にそった認定作業である。正社員賃金には長期雇用の人材確保目的を認定することにより、有期雇用社員賃金との目的の違いを指摘することは容易である。上記最高裁判決によって、そうした違いが両者の基本給の相違が不合理であることの認定を困難にしているとの批判があるが、本判決は上記の論理展開によって、不合理性を認定したものである。
2 専任教員と常勤講師の間において「業務の内容及び業務に伴う責任の程度」に差がないことについては、高校に存在する各種資料を駆使して、年度ごとに全教員のクラス担任、校務分掌、クラブ担任について記載した表を作成し、専任教員と常勤講師を色分けして比較した。原告は、配置転換によって図書室勤務とされたのであるが、ここは資料の宝庫であった。元校長と同僚教員の証言も効果的であった。少なくとも本件訴訟で対象ととしていた令和3年度までの間は、「業務の内容及び業務に伴う責任の程度」がまったく同様であったことは完璧に立証できた。判決も正しく認定している。被告は、さすがにこのままではまずいと考え、令和4年度から校務分掌担当や会議において多少の取り扱いの違いを見せているが、基本的には大きな違いがない。判決は、配転命令を有効としたため、令和4年度以降は専任事務職員との間に賃金差について損害発生を認めており、令和4年度以降の専任教員との賃金差額の認定はしていない。配転命令が無効と認定していた場合、専任教員との賃金差額全額について損害として認定したのか、その一部について認定したのか、裁判所がどう考えていたのか知りたいところである。
3 判決は原告が無期転換した後の請求について、パート有期法8条の適用は否定したものの、「無期労働者である専任教職員と従前は有期労働者である常勤講師であった原告との間に不合理な賃金差があることに変わりはないから、同日以降も原告に専任教員よりも低い賃金しか支給しなかった被告の対応は原告に対する不法行為を構成するといえる。」としている。違法状態を承継しているとしており、妥当な認定である。弁護団は、パート有期法8条・9条の類推、民法90条の適用を主張したが、判決のように認定することにより不法行為を認めることは十分可能である。無期転換してしまうと、労契法20条やパート有期法8条・9条の適用が認められないと議論されてきたが、本判決の理論構成によれば不法行為による損害賠償は認められるはずである。この点においても、本判決の意義は大きい。
■ 今後について
労契法20条違反を争点にした一連の最高裁判決は、一部の手当については労契法20条違反を認定したものの、賃金の中核をなす基本給、賞与、退職金については、労契法20条違反を認めていない。労契法20条は、パート有期法8条として引き継がれているが、一連の最高裁判決以後に、基本給、賞与、退職金について、労契法20条やパート有期法8条違反を認定した判決は、現れていなかった。名古屋自動車学校事件では、原告である嘱託職員らと正社員との間で①業務の内容及び業務に伴う責任の程度、②職務の内容及び配置の変更の範囲については差はなく、この点については最高裁でも特に問題にはなっていない。名古屋高裁が基本給と賞与の格差について60%を下回る範囲は違法であるとしたのに対して、最高裁は原審の判断を覆し、破棄差戻しとした。
こうした中で、労契法20条およびパート有期法8条違反として、基本給について専任教員との差額全額を損害として認定した本判決の意義は大きい。弁護団としては、裁判所にパート有期法9条違反についても認定してもらいたかったところであるが、それは今後の課題としたい。今後、大阪高裁さらには最高裁での闘いとなる。配置転換については、逆転をめざすとともに、賃金差別について本判決が維持できるように努力していきたい。みなさんのご支援、ご協力をお願いする。