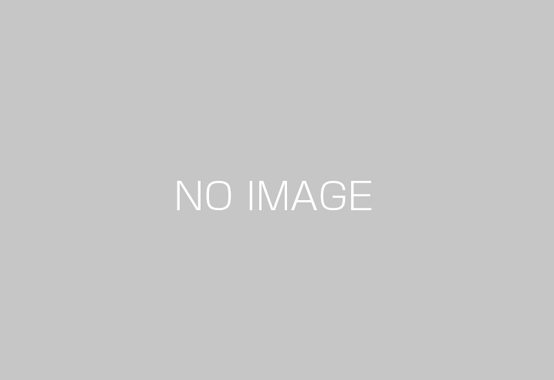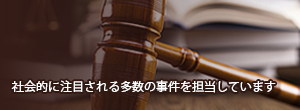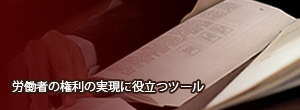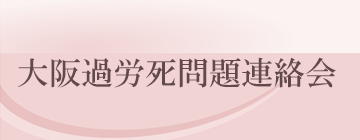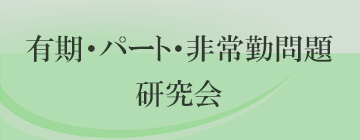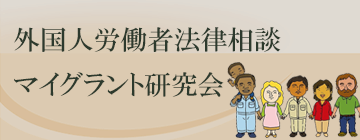第4分科会 激増する外国人労働者、労組に何ができるのか
弁護士 江藤 深
第4分科会は「激増する外国人労働者、労組に何ができるか」というテーマで、労働相談を受けた際に外国人特有の問題をどのように念頭に置いて対応するか、実際の事件を素材にした設例を検討、議論した。参加者はマイグラント研究会所属の弁護士のほか、労働組合、学者、市民団体、報道機関記者ら約30人であった。
冒頭、川村遼平弁護士が、外国人労働者受入れの現状について、在留資格別、国・地域別のグラフを示し、その数は近年右肩上がりであることなどを説明した。また、仲尾育哉弁護士は、在留資格と就労の関係について話し、外国人労働者から相談を受ける際には、まず所持する在留カードに記載のある在留資格、在留期間を確認すべきであること、資格外活動とならないようにマッチングすることが重要であることを強調した。
後半は、大阪でも多く働くベトナム人労働者にまつわる設例で、雇用主に退職を申し入れたところ、身に憶えのない「来日にかかった費用」なる40万円を返還請求された事案、「技能」の在留資格を得てベトナム料理店で勤務する予定であったのにハンバーガーショップで働いていたところ、在留期間満了の直前で解雇された事案、技能実習中に工事現場の足場から転落し、後遺障害が残り得るようなけがを負った事案の3つについて、相談を受けた場合の対応を議論した。
進行役の四方久寛弁護士からは、来日したばかりの労働者は相当額の借金を負っていることが多いため、組合もそれに留意して会社との交渉に当たる必要があること、パワーハラスメントや労災事故の背景、原因にはしばしばコミュニケーションの問題が存在するため、再発防止の申入れもそれを踏まえたものであるべきことなどの説明があった。また労働組合を中心に多数の発言があり、外国人労働者の通院に付き添うときの通訳の確保の難しさや、技能実習が修了した後にも日本で働き続けてもらうための環境整備など、活発な問題提起もされた。
4 / 5