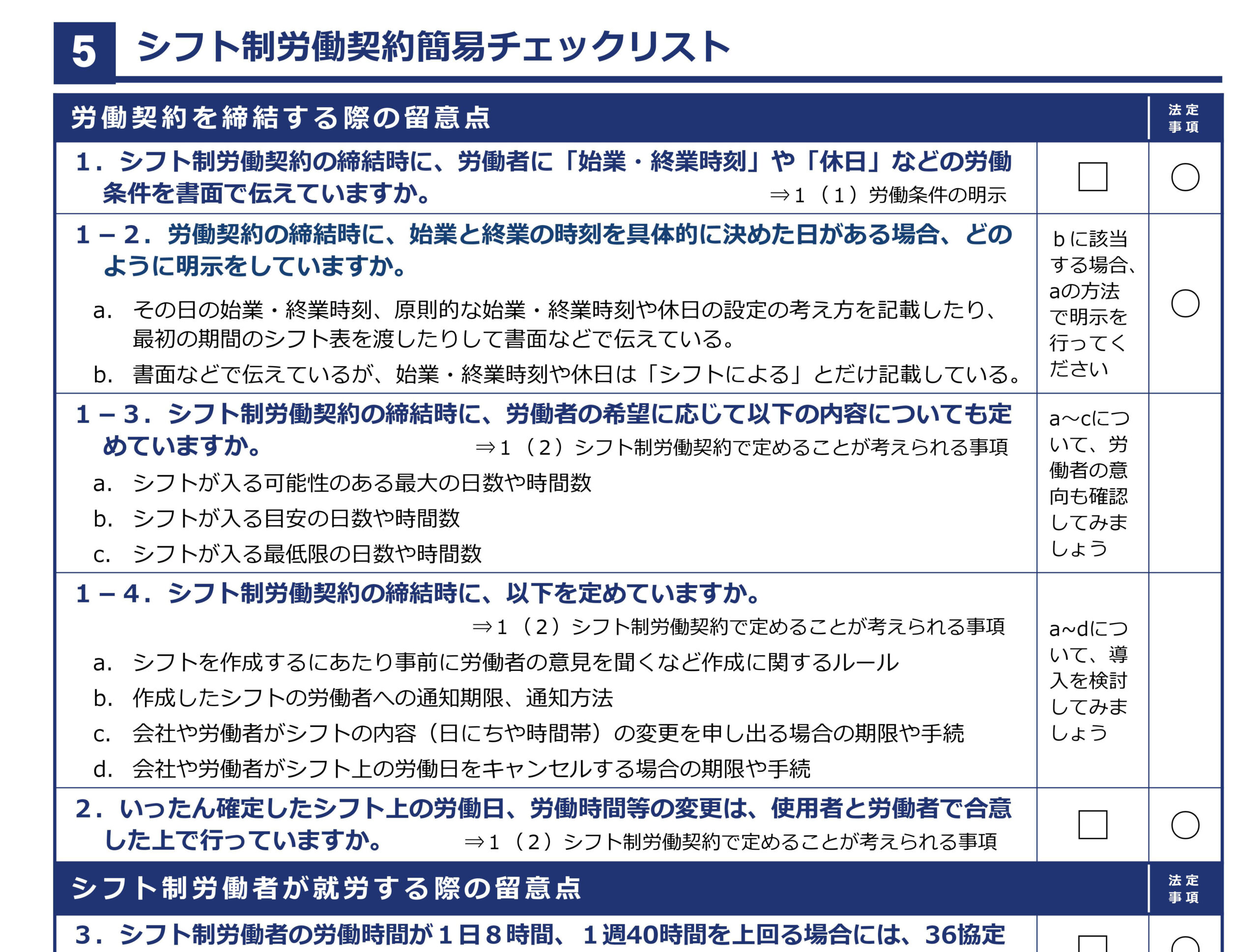弁護士 鎌 田 幸 夫
1 事案の概要と逆転勝訴判決
本件は、2010年4月1日から羽衣国際大学人間生活学部人間生活学科生活福祉コースの非常勤講師として勤務していた控訴人が、2013年3月から専任教員(講師)として3年の有期労働契約を学校法人羽衣学園との間で締結し、2016年4月に、さらに3年間の有期労働契約を更新し、通算期間が5年を経過したので、2018年11月に労働契約法18条1項に基づき無期転換権を行使したところ、法人は、大学教員等の任期に関する法律(以下「任期法」という)の10年特例の適用があり、無期転換権は発生していないとして、2019年3月末をもって控訴人を雇止めしたので、控訴人が法人に対して地位確認請求と賃金請求をした事案である。
大阪地裁は、2022年1月31日、原告の請求を棄却したが、大阪高裁(冨田一彦裁判長)は、2023年1月18日、控訴人の無期転換を認め、地位確認と賃金支払いを命じる控訴人の逆転勝訴判決を言い渡した。
2 本判決の意義
大阪地裁判決は、「講師」は、基本的に「研究者」に該当する旨の国会答弁などを理由に、原告の地位は任期法4条1項1号のうち「その他の当該教育研究組織で行なわれる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究の職」に該当するとして任期法の適用を肯定した。この他に大学の自治の要請から大学に裁量があること(学校法人梅光学院事件・広島高裁判決)や大学の専任講師であること(学校法人茶屋四郎次郎記念学園・東京福祉大学事件・東京地裁判決)を理由に緩やかに任期法4条1項1号該当性を肯定する裁判例がある。
これに対して、科技イノベ活性化法による10年特例が争点となった事案であるが、同法の10年特例は、労契法18条の5年無期転換を認めると、5年を超えるプロジェクトも少なくなく、無期転換回避のために5年を超える前に雇止めされるおそれがあり、プロジェクトの知見が散逸し業績を挙げることができなくなることを回避するためであり、同法15条の2第1項1号の「研究者」とは研究業務及びこれに関連する業務に従事する者であることを要し、ドイツ語の非常勤講師は、教育のみを担当し、研究開発等の業務に従事しないのであるから、「研究者」に該当しないとした裁判例がある(学校法人専修大学事件東京地裁判決、同東京高裁判決)。
本判決は、任期を定めることが合理的な類型であることを明確にした任期法の制定の趣旨と、労働契約法18条1項の5年無期転換の例外である10年特例を設けた任期法改正の趣旨を考慮したうえで、任期法4条1項1号の「教育研究」の職について「先端的、学際的又は総合的な教育研究であること」を示す事実と同様に、具体的事実によって根拠付けられていると客観的に判断し得ることを要するとして任期法4条1項1号の限定的な判断枠組みを初めて示したことに画期的な意義がある。本判決は、控訴人の職は、介護福祉士養成課程の担当教員であり、その募集経緯や職務内容に照らすと、実社会における経験を生かした実践的な教育研究等を推進するため、絶えず大学以外から人材を確保する必要があるなどということはできず、また「研究」という側面に乏しく、「多様な人材の確保が特に求められている教育研究の職」に該当するということはできないとし、任期法4条1項1号の該当性はなく、労働契約法18条1項の5年無期転換の原則が適用されて、すでに無期契約になっているので雇止めはできないと判断し、地位確認等を認めた。
本判決は、全国で係属している同種の事件の勝訴に向けて大きな力となる。また、被控訴人法人のみならず、全国の少なからぬ大学で、改正任期法や科技イノベ法の10年特例の趣旨とは無関係な人件費抑制や労務管理の便宜のため等、都合のよいように科技イノベ活性化法や任期法を利用し、期間雇用教員の職務の内容からして、これらの法の対象でない者を含めてルーズかつ、恣意的に10年特例の対象として扱い、5年無期転換権の行使を阻止し、長らく不安定な地位に置いてきた実態がある。本判決は、このような恣意的な運用に歯止めをかけて、期間雇用教員の5年無期転換による早期の雇用安定を促すものであり、高く評価できる。
3 高裁での勝因
提訴後4年が経過し、地裁で敗訴するなど大変厳しい闘いを強いられてきたが、大阪高裁で逆転勝訴できた要因は、次の3つである。
第1に、控訴人と所属する教職員組合、上部団体である私大教連などが、大阪地裁の金銭解決の和解提案や不当判決にめげず、無期転換の正当性を確信し、最後まで職場復帰を目指して闘ったことである。高裁での控訴人の意見陳述や多くの団体署名や教え子の手紙などが裁判官の心を動かした。
第2に、地裁敗訴後、大学任期法の制定と改正の趣旨に関する早津裕貴金沢大学准教授の意見書と労旬の論文を提出したことである。本判決は、改正任期法の解釈適用の在り方について、早津意見書、論文の論旨を採用したものといえる。
第3に、科技イノベ活性化法の「研究者」を限定的に解した専修大学事件地裁判決が、2022年7月6日の東京高裁判決でも維持されたことである。このことが、大阪高裁が任期法の該当性も平仄を合わせて限定的に解することを後押しした。
4 今後の課題
控訴人や組合の上告断念を求める要請を無視して、法人は上告した。
すでに上告されている専修大学事件と同様、画期的な高裁判決を確定させるために力を尽くしますが、是非大きなご支援をお願いします。
(弁護団は中西基、西川翔大、鎌田幸夫)