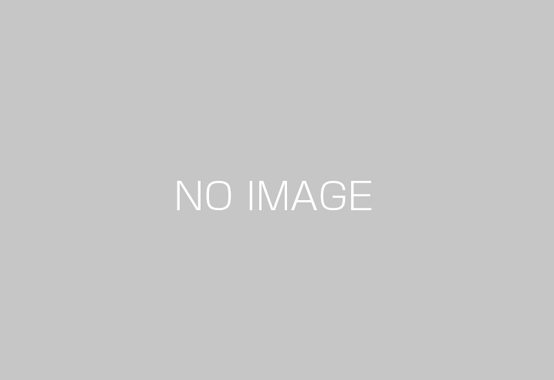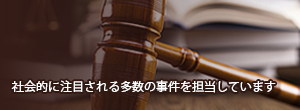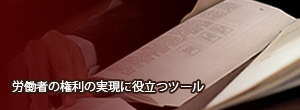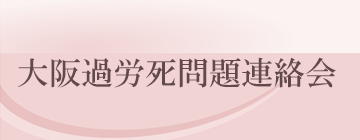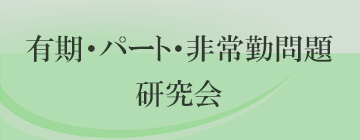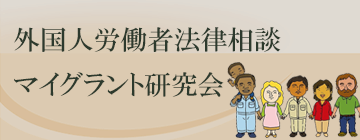弁護士 西川 翔大
1 2025年3月22日(土)、労働法研究会では、前回に引き続き、西谷敏先生(大阪市立大学名誉教授)をお招きして、西谷先生の著作集を題材に報告及び議論を行いました。現地及びZoomで各地の研究者、弁護士、労働組合の方がおよそ30名程度参加しました。
2 まず、今回の研究会では、民法協事務局長の藤井恭子弁護士から、労働基準関係法制研究会報告書(以下「労基研報告」といいます。)やそれに対する民法協の取組み及び意見書についてご報告いただきました。同研究会での議論状況を踏まえて民法協加盟の労働組合に対してヒアリングを実施し、労働現場の実態を意見書に反映する形で労基研報告書に対する意見書を作成した経緯や、「デロゲーション」という言葉が「法定基準の調整・代替」という言葉に置き換えられ、労基法の適用除外が進められる危険性や少数組合について触れられていない点などに対する批判を記載した意見書の内容を紹介していただきました。
次に、私から、著作集第1巻第12章「二つの『働き方改革』」を題材に、「多様化・柔軟化」が進む働き方の中で労働者が求める働き方について報告しました。西谷先生著作集の中から、経済会・政府が「多様化・柔軟化」をキャッチフレーズとして規制緩和を進めようとする中で、労働者・労働組合としては労働者の意識や「働きがい」の諸条件をいかなるものと捉え、対抗していく必要があるのかという西谷先生の問題意識をご紹介しながら、労基研報告に触れつつ、テレワークや副業・兼業で多用される自己申告制の問題や法定基準の制定及び形式的な適用だけでは労働者の働きがいを保つことができず、実質的かつ具体的な要求を検討しなければならないという私の問題意識を述べました。最後に、青木克也弁護士から著作集第1巻第1章「労働法における理念と政策」に基づいて、憲法を頂点とする労働法理念の体系的な理解、日本における労使自治や労働立法の限界、裁判の法政策的機能などについて紹介されたうえで、解雇の金銭解決制度の実現により労働者がより従属的な地位に立たされる危険性、最近の裁判所の脱法行為に対する判断を見ると階層的に築かれた労働法理念が十分に顧慮されていない等の問題意識や判例形成における研究者の役割について述べて頂きました。
3 これらの報告を踏まえて西谷先生からコメントをいただきました。
まず、日本では労働組合の力が弱く、労働者側からの要求ではなく、労働官僚、経済界などの外圧により労働法制が制定されることが多いため、使用者の労働法遵守意識が希薄であり、脱法行為が多発していること、裁判所も法律の実質的な趣旨を踏まえておらず、形式的な文言解釈にとらわれている部分があることを指摘されました。また、日本では「悪法反対運動」はそれなりに展開されるが、本当に必要なのは労働者の立場から見てこういう法律が必要だというものであり、それをどうやって強力な運動としていくのかが課題であるとコメントされました。さらに、今回の労基研報告について、「法定基準の調整・代替」という表現が「デロゲーション」を意味することを明確に意味するものであり、労使自治により法定基準を下回ることが許されることは憲法27条2項に抵触する点、労基研報告が「労使自治の拡大」や「労使コミュニケーション」を強調するものの、憲法28条からすれば本来の労使関係は争議行為が行われ、利害が対立するものであると想定されているため、その前提が誤っていることを批判された上で、現在の労働運動としては規制緩和反対論だけでは、多様で弾力的な働き方を求める現在の労働者の心をつかむことが困難であり、明確に労働者側から求めていくことが重要であるとお話されました。
4 その後の全体での討論では、労働者の働きがいを巡って、やりがい搾取の中に取り込まれる危険性がある点をどう克服するかを意識する必要があるという意見が出ました。また、労働組合の方からは、労働者の中には「仕事だからやらないといけない」という意識があるものの、組合としては自分の仕事に誇りをもって取り組むことを強調しているとか、働きがいを生み出す諸条件の中でも賃金が確保されることは最低限必要だといった意見が述べられました。さらに、労基研の労働者側のニーズに基づいているかのような記載(「支える」の視点)が反論を困難にする部分があるものの、実態を踏まえて適切に批判していく必要があり、特に労働保護法の規範に「法定基準を調整・代替することが許容される基準」があると明確に記載されていることの報告書の危険性に留意する必要があるという意見がありました。
5 今回の労働法研究会では「多様化・柔軟化」をめぐる議論や経済学と労働法理念の対立など労基研報告書の背後にある問題を紐解き、現場の声も含めて、研究者、労働組合、弁護士を会員とする民法協らしい活発な議論を行い、労基研報告書を再考する契機とする事ができました。