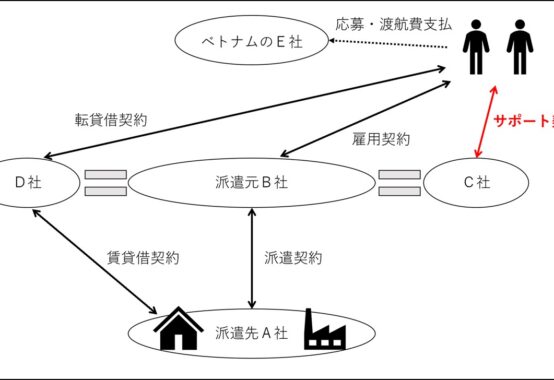弁護士 仲 尾 育 哉
2023年12月5日と同月12日、私が再審情願を受任していた日本で生まれ育ったにもかかわらず退去強制の対象になっていた子どもとその家族、二組に法務大臣により在留特別許可が出された。一組は大阪府内の中学生と東南アジア出身の母親で、子どもと母親ともに在留期間の更新が認められず超過滞在となり、退去強制の対象になっていた。もう一組は大阪府内の高校生と南アジア出身の父親及び母親で、父親の政治活動などを理由に祖国で迫害を受けるおそれがあるとして、家族は難民申請していたが認められず、退去強制の対象になっていた。両組とも10年以上にわたり、入管施設での収容を一時的に解く「仮放免」の状態で、収容はされていないが就労や健康保険への加入などは認められていない中で暮らしてきた。
出入国在留管理庁は2023年8月4日、「送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針について」を発表し、親の超過滞在などにより在留資格がない子どもについて、一定の条件を満たせば家族一体で在留を認める措置を示していた。2022年12月末時点で在留資格のない送還忌避者(退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、各種の事情から自らの意思で日本からの退去を拒んでいる者)4233人のうち日本で出生した子どもは201人おり、その約7割(140人程度)に在留資格が与えられることが見込まれるとされた。二組は、この措置による関西でおそらく一番目と二番目の例である。それぞれ、子どもには「留学」、親には日本の学校に通う子どもを扶養する者として就労可能な「特定活動」の在留資格が付与された。
今回の出入国在留管理庁の対応方針は、改正入管法の施行時までに、日本で出生して小学校、中学校又は高校で教育を受けており、引き続き日本で生活をしていくことを真に希望している子どもとその家族を対象に、家族一体として在留特別許可をするとしている。
これまで入管においては、日本で生まれ育ったにもかかわらず退去強制の対象になっていた子どもとその家族に対し、「親が帰国すれば、子どもの在留を認める」と示され、実際に、子どものみ在留が認められ、両親と離ればなれになった例があった。強制送還で親子を引き離したり、そうした決断を迫ったりすることは、国際人権規約が保障する家族結合権(自由権規約第17条、第23条)や子どもの権利(子どもの権利条約第3条等)を侵害する可能性がある。そのため、今回の出入国在留管理庁の対応方針が「家族一体」として在留特別許可をするとしたことは評価できる。
ただし、今回の出入国在留管理庁の対応方針は、子どもが「本邦で出生して」いることを条件にしており、幼少期に来日した子どもを含まない(出入国在留管理庁によると2022年末時点の「送還忌避者」のうち日本で出生していない子どもは94人いるとされる。)。日本で出生した子どもも、幼少期に来日した子どもも、日本で教育を受け、日本語を身につけ、日本に定着しているという点で差異はなく、両者を区別すべき合理性は認められない。また、今回の対応方針は、子どもが18歳を過ぎている場合を含まない。18歳を過ぎている場合は日本への定着性がより高いとみるべきであり、こうした場合を除外する合理的な理由はない。
さらに、今回の対応方針は、「親に看過し難い消極事情」、具体的には、①不法入国・不法上陸、②偽造在留カード行使や偽装結婚等の出入国在留管理行政の根幹に関わる違反、③薬物使用や売春等の反社会性の高い違反、④懲役1年超の実刑、⑤複数回の前科を有している等の事情がある場合は、その子どもも在留特別許可の対象から除くとしている。出入国在留管理庁は「個別に判断する」とするが、子どもには何ら責任がない親の事情によって、子供が差別されることがあってはならず、親だけを送還するか否かについては、家族結合権の保障や比例原則に照らして、慎重に判断されるべきである。